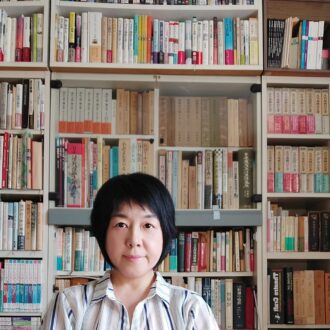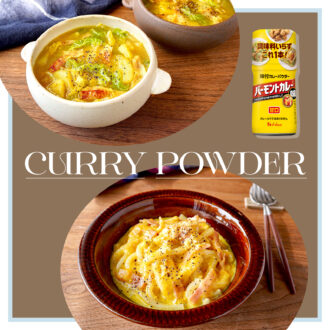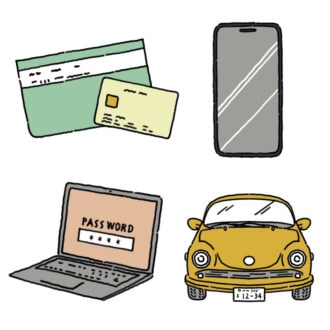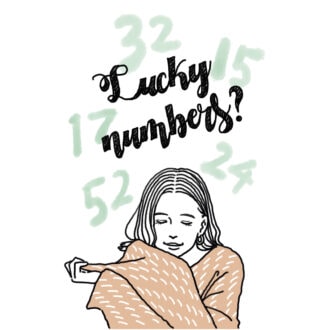OSHI-KATSU
舞台芸術祭『秋の隕石 2025 東京』演劇ジャーナリスト・伊達なつめさんの一押しステージ情報!
執筆者:伊達なつめ
演劇ジャーナリスト・伊達なつめさんのおすすめ作品をご紹介。今回は、舞台芸術祭『秋の隕石 2025 東京』をピックアップ。
奥深く独創的で先進的。芸術に身をゆだねる秋
地球規模の気候変動は夏を長引かせ、秋を侵食しようとしているけれど、「芸術の秋」のイメージと実体は、なんとしてでも死守したい。暑さや寒さに気を取られることなく、少し物事を深く考えたくなってくる10月に、薄っぺらさとは真逆の深遠かつ、虚を衝くほど自由な発想に揺さぶられるために。
先日「巨星墜つ」と訃報が伝えられたばかりのパフォーミングアーツ界の大御所ロバート・ウィルソン。フランスの大女優イザベル・ユペールと組んだ『Mary Said What She Said』は、悲劇の女王メアリ・スチュアートの処刑前の独白を、鮮烈な光と影のコントラストの中でスタティックに表現するひとり芝居だ。ウィルソンの透徹した美意識にも息を呑むし、その徹底的に制御された演出をものともせずに体現する、ユペールの怪物ぶりにも舌を巻く。ウィルソンは、上演に合わせて来日するのを楽しみにしていたという。その偉業に接する、これが最後の機会になるのかもしれない。

©LUCIE JANSCH
透明なガラスビーズで覆われた動物など、粒子を意識した人工素材と自然物を合体させた作品群で目を奪う彫刻家名和晃平。振付家・ダンサーのダミアン・ジャレは、その名和とのコラボで、砂やゲル状素材と人間をからませて、原初の自然界の営みを想起させる、独自の視点による世界を創り上げている。『Planet [wanderer]』では、グレーの地面から、美しく反射する砂の粒子を輝かせて人間が姿を現す。人類の誕生に想いを馳せるようなひとときを共有できるはずだ。
![ダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet[wanderer]』 ©Rahi Rezvan](https://inredweb.jp/official/wp-content/uploads/2025/07/0241a34454ddc8179e9fe99c46fb2b40-800x534.jpg)
©Rahi Rezvan
日本のタニノクロウと台湾の王嘉明(ワン・チャミン)の合作『誠實浴池 せいじつよくじょう』は、煤けた風呂屋のようなSMクラブにやって来る、海で戦死した兵士たちの話。川端康成の『眠れる美女』をベースに、死んでなお自分の身体を痛めつけに訪れる青年の姿が切なく、そこはかとなくいかがわしい。

©Hsuan-Lang LIN, provided by National Theater & Concert Hall
海外でも非常に高い評価を得ている岡田利規の新作『ダンスの審査員のダンス』では、その名の通り、ダンス審査会で審査をしているレジェンド・ダンサーたちが、雑談したり踊り出したりするらしい。そもそも「ダンスのような演劇」と称されるほど身体表現と不可分な岡田ワールド。近年は今回も出演する名プリマ酒井はなとクラシックバレエをテーマにした作品を連続して手がけ、絶賛されている。実力も個性も半端ないダンサー俳優・音楽家たちが複数登場し繰り広げる本作が、おもしろくないわけがないと思う。

©Yusei Fukuyama
これら4作に共通するのは、前例のない驚天動地レベルのユニークさ。天才・鬼才の所業を浴びる秋が、もうすぐやって来る
舞台芸術祭 『秋の隕石 2025 東京』
アーティスティック・ディレクター=岡田利規
10月1日(水)~11月3日(月・祝)
東京芸術劇場、GLOBAL RING THEATRE 他
(問)東京舞台芸術祭実行委員会事務局 TEL:03-6812-1663
文=伊達なつめ
※InRed2025年10月号より。情報は雑誌掲載時のものになります。
※画像・イラスト・文章の無断転載はご遠慮ください。
※地震や天候などの影響により、イベント内容の変更、開催の延期や中止も予想されます。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。
KEYWORD
この記事を書いた人
演劇ジャーナリスト。演劇、ダンス、ミュージカルなど、国内外のあらゆるパフォーミングアーツを取材し、多数の雑誌・webメディアに寄稿。
X:@NatsumeDate
Website:http://stagecalendarcv19.com





![ダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet[wanderer]』 ©Rahi Rezvan](https://inredweb.jp/official/wp-content/uploads/2025/07/0241a34454ddc8179e9fe99c46fb2b40-330x330.jpg)